プレイエル Pleyel グランドピアノ

音色も外観も、とてもきれいなピアノです。
大抵のピアノは、鉄骨に製造番号が記されているのですが、これにはありません。
よく見ると、チューニングピンを支えるピン板は新調されていて、また、駒には本来塗っていないはずのニスが塗られています。
そのようなことから、このピアノはピン板が割れて調律が出来なくなったため、過去に大修理をして、ピン板を新調、鉄骨や響板、駒などを塗り替え、弦を張りなおしたことが分かります。
ピン板には弦の太さを示す番号が書かれているので、弦も新しいもので張りなおしたものと思われます。(古いものを再び使うのはかえって面倒なものです。)
多分、そのとき、鉄骨に書かれていた製造番号などの文字も消えたのではないかと思われます。


Paris France と書かれています。
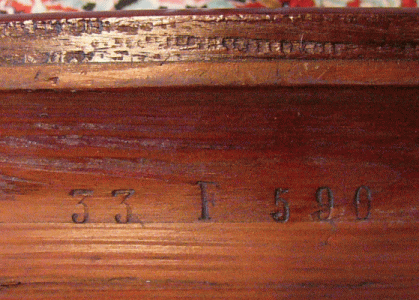

これは写真の撮影に失敗したので、残念ながら掲載できません。

プレイエルはショパンのお気に入りのピアノですが、ショパンは1849年に亡くなっていますので、残念ながらこのピアノを演奏した可能性はありません。
低音弦を効率よく長くとるために、中音弦と交差させる方法がとられています。
古いピアノでは交差せずに中音部と平行に張っているものもよくありますが、交差弦のピアノも古くからあります。
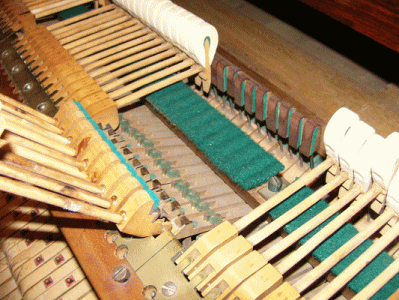
アクションはイギリス式。
現代のピアノと動作原理は同じです。
若干形が違います。
特にハンマーバットの、レールへの取り付け方が異なっています。
ブロードウッドなどの古いピアノもそうなのですが、センターピンがそれぞれのハンマーに独立しておらず、長い針金にバットを数珠繋ぎにしていき、それを真鍮のプレートでハンマーレールに固定します。
そのため、一本のハンマーを取り外そうと思えば、とても面倒なことになります。

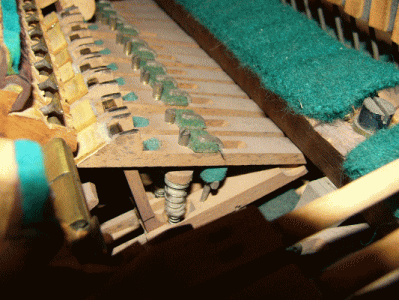
古いピアノに向かい合うことは、大先輩の技術者に向かい合うことと同じです。
許されれば、分解してみたい気持ちになります。 でも、あとがやっかいだから、しません。
 ピアノ技研 今井惠 2008.10.07 pianogiken.com
ピアノ技研 今井惠 2008.10.07 pianogiken.com